- 市場は様子見のレンジ、BTCは11.3万ドル台で小反発
- 米上院が「デジタル資産課税」公聴会を予告、税制の枠組み整理が前進
- SECとCFTCが協調ラウンドテーブルを開催、役割分担と担保トークン化が論点
- イーサリアム:Fusakaを12月3日目標に、L2の料金設計リスクも浮上
- BNBチェーン:ガス半減とブロック短縮提案、DEX主導の需要に対応
- オーストラリア:デジタル資産プラットフォーム規制の素案(背景:保護と明確性)
- DAT・ETF:GSRが5本申請、BitwiseはETHトレジャリーの台頭を指摘
- 地域動向:APACが採用拡大で世界を牽引
- ステーブル/トークナイズ:フランクリンがBNB接続、Bastionは資金調達
- セキュリティとコンプライアンス:州交通当局の流出とFTX債権者向け詐欺
- DePIN:手数料は過去最高、トークン価格は低迷の逆行現象
- 今後の注目イベントとリスク(数日~数週間)
- 結論・要点整理
市場は様子見のレンジ、BTCは11.3万ドル台で小反発
暗号資産市場は様子見です。 ビットコイン(BTC)は$113,414(+1.05%)で小反発しました。イーサリアム(ETH)は$4,156(-0.44%)です。短期は$113,000近辺の攻防が続いています。
きょうのスナップショット
- 時価総額:$3.89兆
- 24H出来高:$1,617.8億
- ドミナンス:BTC 57.8%/ETH 12.9%
値動きは小幅で、方向感は限定的です。
株式・VIX・為替・商品
米株は小安く終了しました。ダウ-0.37%、S&P500-0.28%、ナスダック-0.34%です。大きなトレンドは出ていません。
VIXは16.18です。ボラティリティは落ち着いた水準にとどまっています。
為替はドル高が一服し、USD/JPYは148.67近辺で推移しました。
商品市況はまちまちです。金先物は$3,778台、WTI原油は$64台です。マクロイベント前で、手控えムードが残っています。
用語解説
- 時価総額:すべての暗号資産の「価格×発行量」の合計。
- 出来高:直近24時間で成立した取引金額の合計。
- ドミナンス:主要銘柄が市場全体に占める割合。
- VIX:米株の予想変動率指数。高いほど不安定とされる。
- レンジ相場:一定の価格帯で行き来し、方向感が出にくい状態。
米上院が「デジタル資産課税」公聴会を予告、税制の枠組み整理が前進
上院財政委員会は10月1日に「デジタル資産の課税」をテーマとする公聴会を開く予定です。証言者にはCoinbase(米ナスダック上場の大手取引所・カストディ)の税務担当副社長ローレンス・ズラトキン氏と、Coin Centerの政策ディレクター、ジェイソン・ソメンサット氏が含まれます。先日も取り上げたGENIUS法の事前意見募集と連動する動きで、制度の明確化が進む局面です。
論点の整理
委員会は、既存税法の適用範囲と新たなルールの要否を改めて検討します。ホワイトハウスの「デジタル資産ワーキンググループ」の提言が参照点となります。主な論点は次のとおりです。
- 資産区分の整理:証券・商品に加え、暗号資産を独立区分とする是非。
- 少額決済の非課税案:300ドル以下の取引を非課税とする提案の扱い。
- 支払い時の税率設計:ビットコイン決済などの軽減税率の是非。
- ステーキングやエアドロップの課税時点と計算方法。
- 申告実務:原価計算、ロット識別、情報報告の標準化。
スケジュールの不確実性
連邦政府の歳出関連法案の期限は9月30日です。政府閉鎖となった場合、公聴会が延期される可能性があります。一方で、論点の整理作業は継続する見込みです。
制度設計との接続
今回の公聴会は、GENIUS法の運用設計と並行して進みます。担保や決済での安定性向上を狙う制度に、税制の明確化を重ねる狙いです。課税区分や非課税枠が固まれば、少額決済や会計処理の不確実性が和らぎます。
用語解説
- GENIUS法:米国のステーブルコイン包括法。発行体や準備資産の要件を定める枠組み。
- ANPR:規則案の事前通知。関係者から意見を募る初期段階の手続き。
- 少額決済の非課税(de minimis):一定額以下の売買益に課税しない制度案。
- 上院財政委員会:税制や通商を所管する上院の常任委員会。
- Coin Center:暗号資産の政策提言を行う非営利のシンクタンク。
SECとCFTCが協調ラウンドテーブルを開催、役割分担と担保トークン化が論点
米証券取引委員会(SEC)と商品先物取引委員会(CFTC)は、9月29日に規制の「ハーモナイゼーション(整合)」をテーマとしたラウンドテーブルを共同開催します。暗号資産の所管整理と市場インフラの基準作りを議題とし、Kraken(米系の大手取引所)やCrypto.com(グローバル展開の取引所・決済プラットフォーム)に加え、Kalshi(CFTC認可のイベント先物取引所)やPolymarket(分散型の予測市場プロトコル)の関係者が登壇予定です。人事交代で空席が続くCFTCでは、キャロライン・ファム委員長代行の下での発信となります。
論点の整理
- 監督区分の明確化:証券型と商品型の線引き、両庁の権限配分。
- 市場構造の定義:取引所、ブローカー、清算の要件と登録手続き。
- 担保トークン化:安定通貨などを証拠金に用いる枠組みとリスク管理。
- 情報開示と上場基準:商品型信託の一般基準と審査の簡素化。
- 執行の一貫性:調査・和解・訴訟の運用差を縮める手順設計。
出席予定企業と狙い
現物・先物を扱う大手取引所に加え、予測市場を運営する事業者が参加します。決済や清算の安全性だけでなく、デリバティブとイベント取引を含む新種サービスの扱いが論点になります。オンチェーンの流動性、カストディ、相場操縦対策の実務的な論点を、事業者の運用実態と照らして確認する狙いがあります。
直近の文脈
米下院は7月に市場構造法案を可決し、上院の審議待ちです。SECは商品型信託の汎用上場基準を承認し、審査の標準化を進めました。CFTCは安定通貨を担保として認めるための作業を開始し、業界との対話を拡大しています。今回の協調は、これらの流れを制度面で接続する位置づけです。
用語解説
- ハーモナイゼーション:複数監督当局の規制を整合させる取り組み。
- 市場構造法案:暗号資産の売買・清算・保管の定義と登録要件を定める立法案。
- 担保トークン化:安定通貨などのトークンを証拠金や担保として用いる設計。
- 商品型信託の汎用上場基準:コモディティ連動ETFの上場審査を標準化するルール。
- 予測市場:将来事象を対象に売買し、確率を価格に反映させる市場。
イーサリアム:Fusakaを12月3日目標に、L2の料金設計リスクも浮上
イーサリアムの次期ハードフォーク「Fusaka」は、12月初旬のメインネット実装を目標としています。開発者は10月に3つの公開テストネットで検証を進め、問題がなければ12月3日を目安に本番適用へ移行する計画です。段階的に処理能力を拡張し、費用低減と安定性の両立を図ります。
Fusaka本体では大幅な仕様変更を急ぎません。一方で、適用後に「Blob Parameter Only(BPO)」という小規模フォークを連続実施します。BPO-1でブロブのターゲット/上限を6/9から10/15に引き上げ、さらに1週間後のBPO-2で14/21へ引き上げる方針です。これらはクライアント更新を最小化し、観測しながら安全に容量を拡大する狙いです。
ロールアップ料金の設計課題が指摘
同じタイミングで、主要ロールアップの料金設計に関する課題も示されました。研究チームは、小口トランザクションで料金が過大または過小になる「誤価格」のリスクを指摘しています。対象はPolygon zkEVM、zkSync Era、Scroll、Optimism、Arbitrumです。
問題の根はコストの三層構造にあります。実行計算、データ公開、証明/検証という三つの資源を単一の式に畳み込む設計が多い点です。前払いや返金方式、バッチ確定時の調整などの運用で、特に小口では価格の歪みが起きやすくなります。返金を悪用したスパム送信など、サービス品質の低下を招く恐れも挙げられています。
スケーリング前進と経済設計の両立
研究は「多次元の料金設計」を提案しています。計算、データ、証明を別建てで評価し、実コストに沿って課金する方式です。動的調整や部分的なバッチング、費用内訳の明示なども有効とされます。ゼロ知識証明は需要や機材により費用が変動しやすく、ここを無視すると混雑時に破綻しやすくなります。
FusakaとBPOによるブロブ容量の拡大は、レイヤー2の手数料低減に資する可能性があります。一方で、料金モデルの見直しが伴わなければ、費用の偏りやスパム対策の遅れが残る恐れがあります。技術的な拡張と経済設計の更新が、今後しばらくの焦点となります。
用語解説
- ハードフォーク(Hard Fork):互換性のない仕様変更。旧仕様のノードは新チェーンを検証できない。
- ブロブ(Blob):ロールアップのデータを安価に載せる仕組み。Dencunで導入。
- BPO(Blob Parameter Only):ブロブ関連のパラメータだけを段階的に引き上げる小規模フォーク。
- ロールアップ(Rollup):多くの取引をまとめてL1に投稿する拡張技術。手数料と容量を節約する。
- データ可用性:検証に必要なデータが誰でも取得できる状態を保証すること。
- ゼロ知識証明(ZK):内容を明かさずに正しさだけを証明する暗号技術。検証コストが発生する。
BNBチェーン:ガス半減とブロック短縮提案、DEX主導の需要に対応
手数料とブロック間隔の見直し
BNBチェーンのバリデータは、ガス最小価格の引き下げを提案しました。水準は0.10 Gweiから0.05 Gweiへの半減です。ブロック間隔も750ミリ秒から450ミリ秒へ短縮する案です。目標は平均手数料を約0.005ドルに抑えることです。SolanaやBaseとのコスト競争に対応する狙いがあります。
4月にガスを3 Gweiから1 Gweiへ下げました。5月には0.10 Gweiへ再度引き下げています。段階的な見直しでネットワークの利用コストを下げてきました。今回の提案は、その延長線上に位置づけられます。
取引系トラフィックの拡大
オンチェーンの主役は取引関連トランザクションです。2025年初は全体の約20%でした。6月には約67%に達したとされます。低コスト化はトレーダーと流動性の呼び込みに直結します。提案文でも、超低手数料を成長の核と位置づけています。
Aster(BNBチェーン上の分散型先物DEX)が存在感を強めています。24時間のパーペチュアル取引高は約293億ドルです。日次収益は約720万ドルで、Hyperliquid(独自チェーンの分散型デリバティブ取引所)の約279万ドルを上回りました。トークンASTRは24時間で約37%上昇しました。
競争環境と設計意図
Hyperliquidは自前のドル連動型「USDH」を立ち上げました。発行管理はNative Markets(暗号資産スタートアップ)が担います。準備資産は現金と米国債相当とされます。USDCペアでの取引を開始し、ネットワーク内の担保と決済の自給を目指します。
BNBチェーン側の手数料引き下げは、こうした取引所間競争に合わせた動きです。決済コストを下げ、約定速度を高めることで板の厚みを確保します。結果として、マーケットメイカーの在庫回転を促進します。取引系トラフィックが、インフラ側の設計選択を左右する状況です。
用語解説
- ガス(Gas):トランザクション実行に支払う手数料の単位です。
- Gwei:イーサ換算の最小単位の一つです。手数料水準の表記に用います。
- ブロック間隔:新しいブロックが生成されるまでの平均時間です。
- DEX:分散型取引所です。オンチェーンで注文や決済を行います。
- パーペチュアル先物:満期のない先物契約です。資金調達率で価格を調整します。
- Aster:BNBチェーン上の分散型デリバティブ取引所です。
- Hyperliquid:独自チェーン上の分散型デリバティブ取引所です。
- USDH:Hyperliquidのドル連動型ステーブルコインです。
オーストラリア:デジタル資産プラットフォーム規制の素案(背景:保護と明確性)
枠組みの骨子
オーストラリア政府が、暗号資産事業を金融サービス法の枠内で扱う草案を公表しました。目的は、利用者保護と業界の明確なルールづくりです。草案は「デジタル資産プラットフォーム」と「トークン化カストディ」の新カテゴリーを定義します。これにより、交換、保管、決済などの機能に監督基準が適用されます。
ライセンスと運営要件
事業者はオーストラリア金融サービス(AFS)ライセンスの取得が求められます。利益相反管理、苦情処理体制、最低限のカストディと決済基準の遵守が条件です。顧客資産の分別管理と、プール保管時の統制も明記されました。小規模事業や非金融サービス領域には段階的な適用も想定しています。
対象範囲と移行
草案は、ラップドトークン、公的なトークンインフラ、ステーキングの取扱いにも触れます。従来の枠組みに収まりにくい領域に、専用のルールを当てはめる狙いです。監督当局は豪州証券投資委員会(ASIC)です。施行前の経過措置やガイダンス整備を当局と連携して進める方針です。
国際整合と柔軟性
政府は各国の動向と整合を図る姿勢です。技術進化に合わせ、要件を調整できる仕組みも用意します。硬直的な規制で新規事業が阻害される事態を避けるためです。業界からの意見募集を通じ、最終化までの実務的な調整を進めます。産業育成と消費者保護の両立を目指す構成です。
用語解説
- AFSライセンス:豪州で金融サービスを提供する際に必要な免許です。
- デジタル資産プラットフォーム:暗号資産の交換や決済などを提供する事業体です。
- トークン化カストディ:トークン化された資産を保管・管理する仕組みです。
- ASIC(豪州証券投資委員会):オーストラリアの金融監督当局です。
- ラップドトークン:他チェーン資産を別チェーンで利用できるよう包んだトークンです。
- ステーキング:保有トークンを預けてネットワーク運営に参加し、報酬を得る行為です。
- オーストラリア財務省:金融政策・規制案の策定を担う政府機関です。
- Swyftx(豪の暗号資産取引所):国内大手の一社で、業界意見の発信源となります。
DAT・ETF:GSRが5本申請、BitwiseはETHトレジャリーの台頭を指摘
GSRの申請概要と狙い
GSR(ロンドン拠点のマーケットメイカー・資産運用)は、米SECに5本のETFを申請しました。中核は「デジタル資産トレジャリー企業(DAT)」への投資です。暗号資産を財務に保有する企業の株式に、少なくとも80%を配分します。直接の暗号資産保有を避けつつ、企業のトレジャリー戦略に連動する設計です。
申請には、ETHのステーキング収益に連動する商品群も含まれます。これらは、現物保有や運用を代替し、日々の流動性を確保する運用方針を示しています。個別銘柄ではなく、テーマや戦略に基づくエクスポージャーを提供します。
ファンドの内訳
- Digital Asset Treasury Companies ETF:DAT企業の株式に投資。
- Ethereum Staking Opportunity ETF:ETHの価格とステーキング報酬を反映。
- Crypto StakingMax ETF:PoS資産を中心に資本成長を狙う。
- Crypto Core3 ETF:BTC・ETH・SOLのバランス配分を想定。
- Ethereum YieldEdge ETF:ETHのステーキングにデリバティブを組み合わせ、利回り強化を志向。
審査環境と制度面の追い風
先週、SEC(米証券取引委員会)が「汎用の上場基準」を承認しました。コモディティ型トラストの上場プロセスが整理され、要件を満たす商品の審査が効率化されます。今回の申請は、その枠組みを想定したタイミングです。市場にはBTCや複数アルトのETF案件が並び、商品設計の多様化が進んでいます。
GSRは米国で資産運用部門を立ち上げています。DATテーマやステーキング報酬の取り込みは、企業財務とオンチェーン収益の橋渡しとなります。規制の整備に合わせ、株式・デリバティブ・ステーキングを束ねる構成が広がる局面です。
BitwiseがみるETHトレジャリー需要
Bitwise(米系の暗号資産運用会社)は、ETHを「プログラマブルな財務資産」と位置づけました。報告書は、トレジャリーによるETHの採用が拡大し、ネットの新規供給を上回る構造的需要を生むと分析します。根拠は、手数料収入とMEV(マキシマル・エクストラクト・バリュー)に基づく実収益です。
ETH現物ETFは、BTCと同様の資金経路を持つとされます。ただし、規模は相対的に小さい見込みです。DATとステーキング商品が並走することで、現物・株式・利回りの三つ巴の需要が形成されます。企業の資本政策とオンチェーン経済が接続し、資金循環の多層化が進みます。
投資家への含意
DAT連動型は、企業の暗号資産方針に賭ける間接エクスポージャーです。個別コインの価格ではなく、企業の財務と資本市場の評価が収益源となります。一方、ETHステーキング連動は、利回りの取り込みが鍵です。運用上の上限(たとえば流動性やデリバティブ管理)に注意が向きます。
制度面では、上場基準の共通化が審査の透明性を高めます。商品間の比較が容易になり、テーマ別の資金配分が進みます。結果として、企業財務、現物ETF、ステーキングの三領域で、資金流入の波が段階的に発生する構図が想定されます。
用語解説
- GSR(ロンドン拠点のマーケットメイカー・資産運用):トレーディングと運用、VCを手掛ける企業。
- Bitwise(米系の暗号資産運用会社):指数連動商品やリサーチで知られる運用会社。
- DAT(Digital Asset Treasury):企業が暗号資産を財務に保有するモデル。
- ETF:取引所に上場する投資信託。日中売買が可能。
- 汎用上場基準:取引所に共通の基準を設け、審査を効率化する制度。
- ステーキング:PoS型ネットワークでトークンを預け、報酬を得る仕組み。
- MEV:ブロック生成時の取引並べ替え等で得られる超過価値。
- PIPE:上場企業が機関投資家に私募で株式等を売却する手法。
地域動向:APACが採用拡大で世界を牽引
アジア太平洋(APAC)の暗号資産利用が拡大しました。過去12か月(2024年7月〜2025年6月)で、オンチェーン取引量は1.4兆ドルから2.36兆ドルへ増加しました。牽引役はインド、パキスタン、ベトナムです。
主要ポイント
- APAC:取引量が1.4兆→2.36兆ドルに拡大。
- 中南米:取引量が前年比+63%。
- 北米:受取額は約2.2兆ドル。制度明確化とETF承認が後押し。
- 欧州:受取額は約2.6兆ドルで高水準。
- ドライバー:規制の明確化、取引所やウォレットの普及、送金ニーズの増加。
背景と意味合い
APACでは制度整備とインフラ拡充が並行しました。現地の取引所やウォレットが広がり、個人送金や小口決済の需要も増えました。結果として、草の根の利用が量的な伸びにつながりました。
北米と欧州は金額面で依然大きい状況です。現物ETFの承認が資金の導線を作り、規制の明確化が機関投資家の参加を促しました。地域ごとの強みは異なりますが、全体として利用の裾野が広がっています。
用語解説
- Chainalysis(ブロックチェーン分析企業):取引データを分析し、年次レポートを公表する企業。
- APAC(アジア太平洋):アジアとオセアニアを含む地域区分。
- オンチェーン取引量:ブロックチェーン上で観測される資金移動の総額。
- 現物ETF:現物の暗号資産を裏付け資産とする上場投資信託。
- 制度整備:法律や監督ルールの明確化や運用体制の構築。
ステーブル/トークナイズ:フランクリンがBNB接続、Bastionは資金調達
ステーブルコインとトークン化の流れが拡大しています。フランクリン・テンプルトン(米大手資産運用会社)のトークン化基盤「Benji」がBNBチェーン(バイナンス発のレイヤー1)と接続を発表しました。企業向けの発行基盤ではBastion(ブランド型ステーブル発行のインフラ企業)が1,460万ドルを調達しました。低コストの決済レールと企業主導の発行モデルが、RWA(現実資産)とステーブルの導線を広げています。
BenjiがBNBチェーン統合:低コストでRWAの流通を拡張
Benjiは、従来のトークン化商品に加え、BNBチェーン上での配布と決済を可能にします。ガス代が低く、決済が速いネットワークを採用することで、小口の送受金や決済の利用場面を増やす狙いです。これにより、RWAやファンド型のトークン化商品を、より広いユーザー層へ届けやすくなります。
同時に、既存の投資家向けサービスとブロックチェーン上の流通が結びつきます。伝統資産のトークン化と日常的な決済を近づける取り組みが、一体のエコシステムとして動き出しています。
Bastionが1,460万ドルを調達:ブランド型ステーブルの実装を後押し
Bastionは、企業が自社ブランドのステーブルコインを発行できる基盤を提供します。今回の資金調達はCoinbase Ventures(米上場の大手暗号資産取引所のVC)やa16z crypto(暗号資産特化VC)、ソニーやサムスンのベンチャー部門などが参加しました。資金は、発行・運用に必要なウォレットや法定通貨オフランプの提供、コンプライアンス対応の強化に充てられます。
企業が自前の決済トークンを持つと、決済コストの見通しが立てやすくなります。加えて、ポイントや会員基盤と結びつけた新しい送金・決済体験の設計が可能になります。業界では、発行体が増えるほどユースケースが多様化し、ステーブル利用の裾野が広がるとの見方が出ています。
全体像:RWA×ステーブルの「二層化」が進む
ネットワーク側では、BNBチェーンのような低コスト・高速のレイヤーが整備されています。一方、発行側では、Bastionのような企業向けの共通基盤が拡大しています。この二層の進展が並走することで、発行から流通、決済までの一気通貫が進みます。結果として、RWAの受け皿とステーブルの利用場面が同時に拡張します。
用語解説
- フランクリン・テンプルトン:米大手の資産運用会社。トークン化領域にも展開。
- Benji:フランクリンのトークン化プラットフォーム。ブロックチェーン上で商品の発行・流通を支援。
- BNBチェーン:バイナンス関連のブロックチェーン。低コスト・高速処理が特長。
- Bastion:企業向けのホワイトラベル型ステーブル発行基盤を提供する企業。
- ステーブルコイン:価格が法定通貨などに連動する暗号資産。決済や送金で使いやすい。
- RWA(現実資産):債券や不動産など、実世界の資産をトークン化したもの。
- ホワイトラベル:提供元の仕組みを使い、企業が自社ブランドでサービスを提供する方式。
- オフランプ:暗号資産を法定通貨へ交換して出金する経路やサービス。
- Coinbase Ventures:Coinbaseの投資部門。暗号資産・Web3企業に出資。
- a16z crypto:Andreessen Horowitzの暗号資産特化ファンド。
セキュリティとコンプライアンス:州交通当局の流出とFTX債権者向け詐欺
セキュリティ事案が相次ぎました。米メリーランド運輸局(州政府機関)でのデータ流出と、FTX債権者を狙う偽エアドロップ詐欺です。規制整備の動きとは別に、利用者保護と情報管理の重要性が浮き彫りになりました。
州交通当局でデータ流出:30BTCで競売の情報
メリーランド運輸局の関連システムで、不正アクセスが確認されました。個人情報を含むデータが流出し、復旧対応が続いています。流出データは、ランサムウェア集団Rhysida(サイバー犯罪グループ)により、30BTCで競売に出されたと報じられています。
公開情報によれば、氏名、住所、生年月日、社会保障番号などが含まれる可能性があります。暗号資産は送金の追跡が難しい場合があり、ランサム要求に使われることがあります。米当局は、2024年のランサム支払い額を減少傾向と報告していますが、被害自体は継続しています。
FTX債権者を狙う偽エアドロ詐欺が拡散
FTX(破綻した大手暗号資産取引所)の債権者に向けたフィッシングが拡散しています。流出情報を悪用したメールが届き、「トークン配布」を装う偽の請求サイトへ誘導します。ウォレット接続を促し、資産移転の承認を取る手口が確認されています。
コミュニティ関係者は、Kroll(リスク管理・債権者管理を担う調査会社)の情報流出を踏まえ、詐欺が横行していると警告しています。SBFことサム・バンクマン=フリードのXアカウント再開も報じられましたが、第三者運用の表記があり、なりすましや誤認の懸念が残ります。
用語解説
- ランサムウェア:データを暗号化し、身代金を要求する不正プログラム。
- Rhysida:教育・医療・政府機関などを標的とするランサムウェア集団。
- メリーランド運輸局:米メリーランド州の交通関連機関。鉄道などを所管。
- FTX:2022年に破綻した大手暗号資産取引所。多数の債権者が存在。
- Kroll:リスク・コンプライアンスの調査会社。債権者関連の業務も担う。
- エアドロップ詐欺:無料配布を装い、ウォレット接続や署名を誘導する手口。
- ウォレット接続:DAppsとウォレットを連携する操作。権限付与を伴うことがある。
- BTC建て要求:身代金などの支払いをビットコインで指定する形態。
DePIN:手数料は過去最高、トークン価格は低迷の逆行現象
分散型インフラ(DePIN)で利用が伸びています。手数料収益は過去最高圏です。一方で、主要トークンの価格は下落が続いています。利用増と価格が同時に動かない構図が見えます。キャッシュフローとトークン価値の結び付けが、次の論点として浮上しました。
Heliumが牽引、手数料は最高水準へ
Helium(分散型無線ネットワーク)が収益を押し上げました。8月中旬から9月下旬にかけての5週間で、週あたり約33万〜37万ドルの手数料を計上しました。セクター全体の約6割を占める水準です。SolanaのSeekerフォン連携などが、需要を底上げしました。
他の主要プロトコルも寄与しました。Geonet、Akash Network(分散型クラウド)、Hivemapper(地図作成ネットワーク)の合計は、直近週で約18.1万ドルでした。セクターの手数料はこのところ最高値圏に達し、実利用の拡大を示しています。
価格は年初来で軟調、設計の論点が前面化
一方で、トークン価格は年初来で大幅安が目立ちます。Render、Filecoin、Heliumなどが年率で40〜70%下落した事例が報告されています。利用が増えても、価格に直結しないことがあります。設計と資本配分の課題が背景にあります。
- 手数料がノード運営者に分配され、トークン保有者に直接還元されにくい。
- インフレ率やベスティングで、売り圧力が継続しやすい。
- 収益通貨がステーブル中心で、トークン買い需要に結び付かない。
- 金利環境で、将来収益の割引率が高止まりし、評価が抑制される。
今後は、収益の一部をトークン価値へどう橋渡しするかが焦点です。買い戻し、手数料の一部焼却、ステーキング報酬の設計など、実装の巧拙が評価に影響します。実ネットワークの稼働と、金融的な価値設計を同期させる取り組みが求められます。
用語解説
- DePIN:分散型物理インフラの総称。無線、地図、クラウドなどの実世界サービスを提供。
- Helium:IoT/携帯通信の分散型無線ネットワーク。ノード運営で手数料を獲得。
- Akash Network:分散型クラウド。計算資源の貸し借りをオンチェーンで管理。
- Hivemapper:走行データで地図を作成するネットワーク。投稿者に報酬を付与。
- Geonet:測位・地理情報系のDePIN。センサー由来データの提供を想定。
- 手数料収益:ネットワーク利用で発生する料金。オンチェーンの実需を示す指標。
- トークン経済設計:供給、報酬、買い戻しなどのルール。価値形成の根幹。
今後の注目イベントとリスク(数日~数週間)
本日9月25日の米国GDP確報と、9月26日のPCEデフレーターが金利観を左右します。指標が強ければ利下げ観測は後退しやすいです。暗号資産は金利と為替の影響を受けるため、短期の振れが出やすい局面です。
直近の経済指標(9月25日~9月26日)
9月25日に四半期GDPの確報値が公表されます。個人消費と在庫の寄与が焦点です。9月26日にはPCEデフレーターが発表されます。米FRBが重視する物価指標であり、市場金利の再調整につながります。
同じく9月26日はスイス国立銀行(SNB)の政策金利発表日です。欧州通貨が動けばドル指数の変動を通じて、暗号資産のリスク選好にも波及します。
政策・規制イベント(翌週~10月1日)
翌週、SECとCFTCが規制協調(ハーモナイゼーション)を議題に円卓会議を開催します。現時点で具体的な日時は公表されていませんが、市場構造や担保の扱いが論点です。
10月1日には上院財政委員会で「デジタル資産課税」に関する公聴会が予定されています。課税区分や少額決済の非課税案など、実務上の論点整理が進む見通しです。
カンファレンスと流動性(9月下旬~10月上旬)
9月下旬から10月上旬にかけて、Token2049やEBCなどの業界イベントが連続します。発表や提携で個別テーマが動きやすい一方、資金が一部セクターに偏る場合があります。時間帯によって出来高が薄くなる点にも注意が必要です。
短期のリスク要因(9月下旬以降)
- 現物・先物ETFの資金フロー鈍化:買い需要が弱まり、反発力が低下しやすい。
- 為替のドル高局面:ドル建て調達コストの上昇がリスク選好を抑制。
- レイヤー2手数料設計の脆弱性:小口取引の誤価格がスパムやDoSの温床となる可能性。
- イベント集中:材料出尽くしや見通しの変化でボラティリティが拡大。
これらは複合して作用します。経済指標のサプライズと規制ヘッドラインが重なると、短時間で価格が振れやすくなります。週またぎのポジション管理では、流動性の変化に留意が必要です。
用語解説
- GDP確報:四半期国内総生産の最終推計値。改定で成長率が変化することがあります。
- PCEデフレーター:個人消費の物価指数。米FRBが重視するインフレ指標です。
- SNB:スイス国立銀行。政策金利の変更が為替市場に影響します。
- SEC:米国証券取引委員会。証券の開示と市場監督を担います。
- CFTC:米国商品先物取引委員会。先物・デリバティブ市場を監督します。
- ETFフロー:ETFへの資金流入出。需給の変化を映す指標です。
- レイヤー2(L2):基盤チェーンの外で処理を行う拡張技術。手数料や遅延の低減を狙います。
- ロールアップ:取引をまとめて処理し、結果を基盤チェーンへ記録する仕組みです。
結論・要点整理
本日の軸は「政策前進×L2前進」です。ビットコインは11.3万ドル台でレンジを維持する一方、規制・税制・上場基準の整備と、イーサリアムのFusakaおよびL2の料金設計課題が並行して進んでいます。直近は9月26日の米PCEと、来週のSEC×CFTC円卓、10月1日の米上院公聴会が需給の触媒になります。
全体像の要点
- 価格と需給:BTCは11.3万ドル台で小反発しつつも、方向感は限定的。
- 政策・制度:SEC×CFTCの協調議論と、10月1日の「デジタル資産課税」公聴会が具体論を前進。
- 技術・ネットワーク:ETHはFusakaを12月3日目標。L2では小口手数料の誤価格リスクが指摘。
- インフラと手数料:BNBチェーンはガス半減・ブロック短縮を提案。取引系需要が設計を牽引。
- 採用トレンド:APACの取引量が拡大し、制度整備と受け皿拡充が並走。
- セキュリティ:行政当局の情報流出とFTX債権者向け詐欺が発生し、利用者保護の重要性が再確認。
直近の着目日程
- 9月26日:米PCEデフレーター公表(インフレ観測の鍵)。
- 翌週:SEC×CFTCの規制協調ラウンドテーブル(市場構造・担保の扱い)。
- 10月1日:米上院財政委「デジタル資産課税」公聴会(課税区分・少額非課税など)。
本記事にはAIによる収集・分析データが一部含まれます。情報の正確性には十分留意していますが、最終的な判断はご自身の責任でお願いします。
また、本記事は投資判断を促すものではなく、市場理解を目的とした情報提供にとどまります。













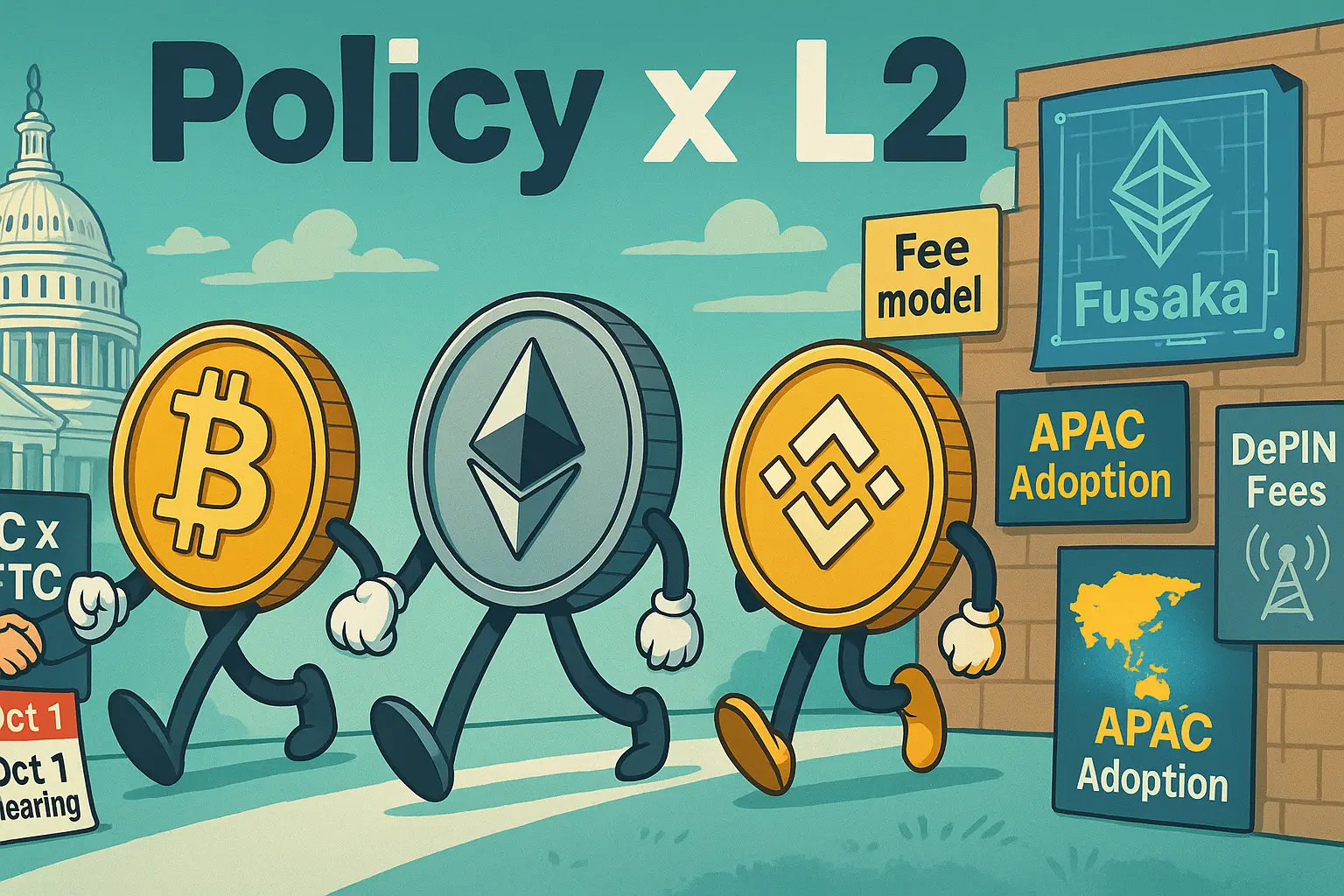

コメント